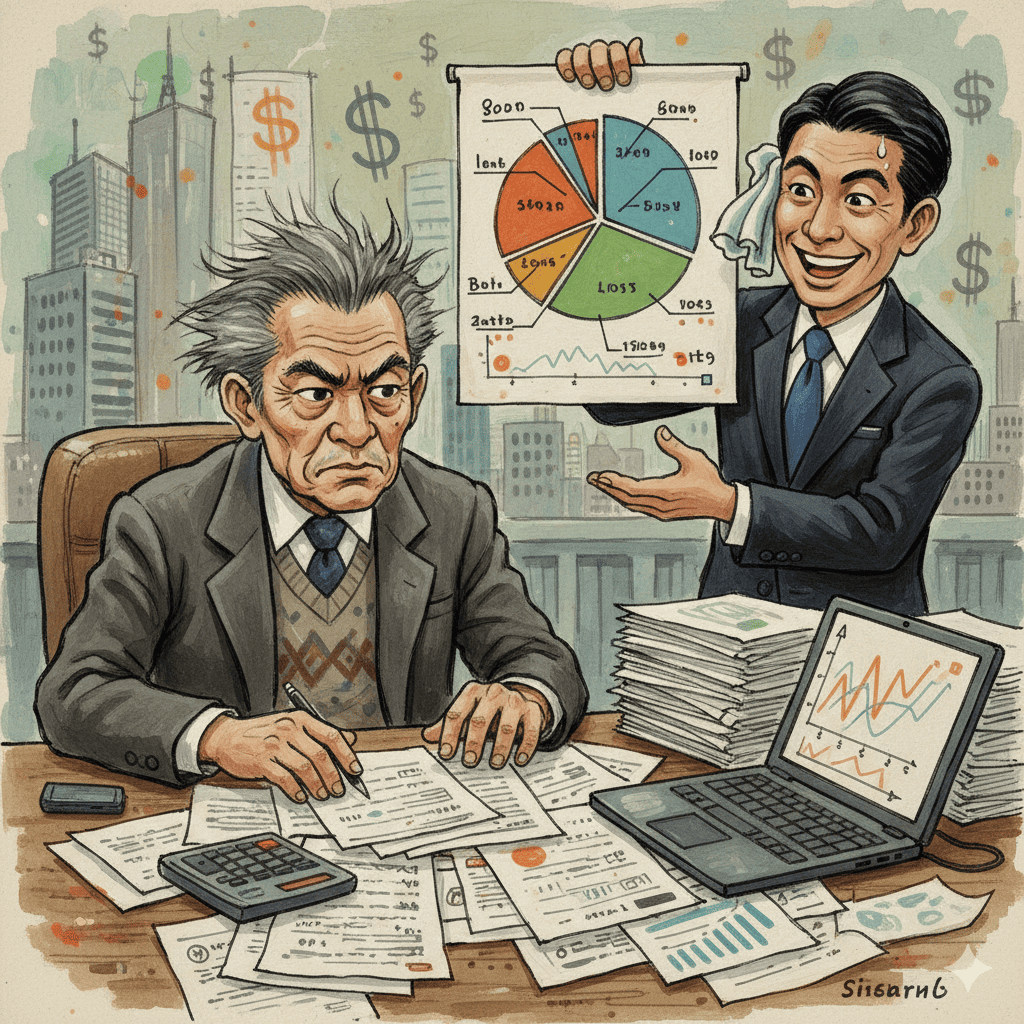9億円の節税プランが「逆転敗訴」に。
野々市・金沢・白山市を中心に活動している「かわした税理士のブログ」へようこそ!
いろいろ頭をひねって、節税スキームを考える人もいれば、
そうはさせじと対策を考える財務省がいます。
はてしなく続くいたちごっこ。
相続税では総則6項が問題となっています。
国が決めたルールにしたがって計算したのに、
それはダメです、と国が主張し、裁判所も同調する。
「だったらそのルールは何?何に従えばいい?」
となりますよね。
東京高裁R7.6.19判決をAIに解説してもらいました。
難しい話なので、分かる人は参考にしてください。
=====
「役所が定めた公式ルール(通達)に従って計算したのだから、税務署に文句を言われる筋合いはない」。こうした、多くのビジネスパーソンや資産家が抱く「ルール遵守=正解」という常識が、今、司法の場で根底から揺さぶられています。
今回取り上げるのは、ある資産家が相続直前に巨額の現預金を株式に転換し、株価評価を劇的に引き下げた節税策が、裁判所によって「租税負担の公平に反する」と否認された事例です。結果として、納税者は約9億7,000万円もの追徴課税という衝撃の結末を突きつけられました。
本判決が突きつける「驚きのポイント」は以下の3点です。
• 「通達」は絶対ではない:令和4年最判のロジックに基づき、行政の内部指針(評価通達)に従っていても、それが「客観的な交換価値(時価)」を反映していなければ否認される。
• 「約48%の減税」は看過し難い不均衡:軽減割合だけでなく、約9.8億円という「減額幅の絶対額」そのものが、他の納税者との不平等を招く「著しい」ものと断じられた。
• 「現金化の計画」が不当性の決定打に:節税目的を隠して「経営上の判断」と弁明しても、相続後に株式を再び現金に戻す「出口戦略」まで記録されていたことが、租税回避の意図を浮き彫りにした。
ポイント1:通達に従えば「正解」ではない――「時価」の真の定義
相続税の計算において、国税庁が定めた財産評価の指針(評価通達)は絶対的な基準と見なされがちです。しかし、本件の東京高裁判決は、相続税法22条の「時価」の本質に立ち返り、極めて峻烈な判断を下しました。
裁判所は、評価通達はあくまで行政内部のマニュアルに過ぎず、国民や裁判所を拘束する法的効力はないとした上で、令和4年最高裁判決の基準を引用して次のように判示しました。
「相続税の課税価格に算入される財産の価額は、当該財産の取得の時における客観的な交換価値としての時価を上回らない限り、同条に違反するものではなく、このことは、当該価額が評価通達の定める方法により評価した価額を上回るか否かによって左右されない」
本件における焦点は、非上場株式の評価額です。納税者側は、通達の計算式を使い1株当たり「1,858円」と申告しました。しかし、裁判所はこれを認めず、純資産価額方式に基づき、より実態に近い3,443円を「客観的な交換価値としての時価」として認定しました。
さらに注目すべきは、納税者側が主張した「非流動性ディスカウント」や「マイノリティ・ディスカウント」の拒絶です。裁判所は、対象会社の資産の大部分が現預金や投資有価証券といった流動性の高い金融資産であり、親族で支配権を握っている以上、換金に追加コストはかからず、価値を割り引く合理的理由はないと一蹴したのです。
ポイント2:「48%の軽減」は「著しい」と見なされる
この裁判で激しく争われたのは、通達評価による節税が「実質的な租税負担の公平に反するほど著しいかどうか」という点でした。
納税者側は、「税額の軽減割合が5割に満たない(約48.1%)のであれば、社会通念上『著しい』とは言えない」と主張しました。しかし、司法の秤は「割合」ではなく「金額の規模」を重く見ました。
本件で節税策を講じなかった場合(現預金のまま相続した場合)の課税価格の合計額は、実に 3,833,988,000円 に上ります。対して、通達による圧縮後の評価額は 2,125,134,000円。このスキームによって減少した納税額は、正確には 978,724,900円 にも達しました。
裁判所は、約10億円近いこの巨額の減額幅そのものが、他の納税者との間に「看過し難い不均衡」を生じさせると判断しました。「節税スキームを構築できる立場にある者だけが、これほど巨額の負担を免れることは、租税負担の公平性を著しく損なう」という論理です。特定の計算式をハックして算出された数字は、実質的な公平性の前では無効化されるという厳しい教訓です。
ポイント3:証券会社との「相談記録」が決定打に
なぜ、これほどまでに厳格な「実質判断」が下されたのか。その背景には、相続開始のわずか3ヶ月前に行われた、生々しい「節税コンサルティング」の記録がありました。
被相続人が90歳を迎える目前、相続人は証券会社と連日のように協議を重ねていました。その狙いは、約40億円の預金を活用し、「株式保有特定会社」や「比準要素数1の会社」といった、株価が高くなる評価区分を回避するための極めてテクニカルな調整を行うことにありました。
相続人側は「これは経営支配権を維持するための資金プール計画であり、節税は副次的効果だ」と弁明しましたが、内部記録は別の真実を語っていました。
「被控訴人(相続人)が、本件新株発行等が近い将来発生することが予想される被相続人からの相続において被控訴人らの相続税の負担を減じさせるものであることを知り、かつ、これを期待して、あえて本件新株発行等を行ったことは明らか」
決定打となったのは、相続後に株式をいかにして効率よく「現金化」するかまで、相続の数ヶ月前から計画されていた点です。経営上の必要性を示す証拠はなく、むしろ「通達を逆手に取って一時的に課税価格を圧縮し、相続後に元の状態に戻す」という租税回避の意図が明白であると断じられました。
分析とリフレクション:形式的平等の終焉
この判決は、日本の相続税対策における「形式的平等」の時代の終焉を象徴しています。通達というルールの「穴」を突き、意図的に評価が下がる状態を作り出す(恣意的な状態形成)行為は、もはや「適法な節税」とは認められなくなっています。
かつては「ルール通りであれば通る」という予測可能性こそがリーガルリスクの防壁でした。しかし、本判決が示したのは、あまりに極端で不自然な対策は、後から「実質」という名のメスで一蹴されるリスクを常に孕んでいるという現実です。資産家やビジネスパーソンは、単なる税率の低減ではなく、その対策が「租税正義」に照らして説明可能かという、より高度な視点を求められています。
結び:未来への問いかけ
ルールをハックし、数字上の「最適解」を導き出すことに夢中になるあまり、私たちは税金の本来の目的である「公平な負担」という大原則を忘れてはいないでしょうか。
今回の判決は、法の網の目を潜り抜ける巧妙なスキームに対し、司法が「法の精神」をもって立ち塞がった歴史的な事例です。私たちは今一度、自問する必要があります。
「ルールをハックすることに夢中になり、税金の本来の目的である『公平な負担』を忘れてはいませんか?」
=====
以上です。